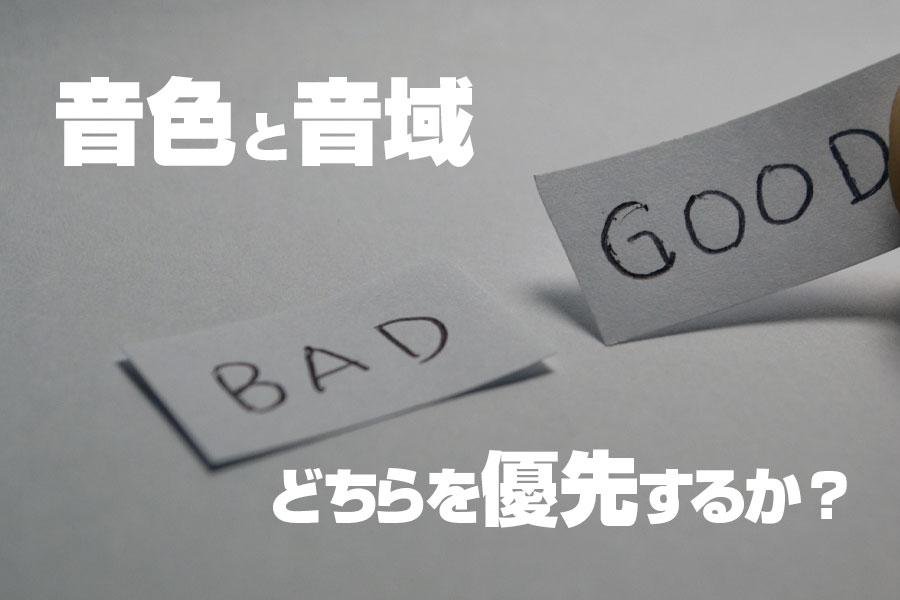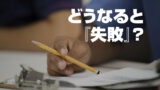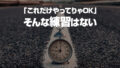疑問・質問フォームに来た質問への回答記事です。質問の本文はこちら↓(回答まとめページはこちら)
- アンザッツ4と6を使って裏声を鍛えているのですが、hiC#辺りから少しずつ閉鎖が混ざり、5番的な音色に近づいてしまいます。
そのためメインの練習はhiC#程度までに留めて、時々上の音域に挑戦するようにしています。
高音を開発するためには高いところの裏声が重要だと認識していますが、狙った発声ができていない場合は上の音域を開発するのは控えるべきですか?
ある程度は許容して、上の音域も開発しても良いでしょうか?
- 以前にも記事にしていたはずですが、練習する際に強度と精度のどちらを優先すべきか?というお話ですね。
めちゃくちゃシンプルな回答としては「どっちもバランスよくやってください」ということになります。
アンザッツとしての精度がほぼ完璧に保てる範囲でのみ練習を続ける、逆に精度を犠牲にし狙った状態にはなってないけど音高はどんどん広げていく、これらのどちらか一方の方向性でのみ練習を続けてしまうと、恐らく中々成長・変化が起こらないか、どんどん余計な癖・固着が強くなってしまうでしょう。
また記事にして詳しく回答しますので、しばらくお待ち下さい。
- 音高が高くなると狙い通りの音色にならない
- 狙った音色にならないのを許容して音高を上げて練習してもいいのか?
質問内容をまとめるとこんな感じ。
狙った状態になってないのを許容して開発を進めていいのか、それとも慎重に狙った状態を保てる範囲で練習すべきなのか、どうしたらいい?ということですね。
以前にも似たようなテーマで記事を書いている↓ので、こういった↑ことでお悩みの方はこの記事と併せて読んでいただくと何か参考になるかもしれません。
音色と音域|それぞれに影響する喉の動き
- 音色
主に声道の形/大きさによって決まる - 音域
主に呼気量/呼気圧や声帯振動のさせ方によって決まる
この記事では解説を単純にするため、このように↑考えてみましょう。もちろん実際にはそれぞれの要素が多分に含まれているわけなので、簡単に分けて考えるのは全く正しくないですが、今回に限りざっくりとこのイメージで話を進めていきます。
今回のテーマに照らし合わせると、低/中音域であれば声道の形/大きさの操作が狙い通り(広く・大きいまま)にできるけれど、高音域になり呼気量が増えたり声帯振動を増やすための動作が多くなるとそれが崩れだす(狭く・小さくなる)ということになります。
そして練習の方向性として、音色を犠牲に音域を広げる方が良いのか、音域はさておき音色を維持できる範囲で練習する方がいいのか?というお話です。
どちらの方向性でも偏ると面倒なことになる
- 音色は度外視してどんどん音域を広げる
- 音域は度外視し、音色を優先して慎重に練習する
このどちらに偏っても良くないです。しかし独学で練習している方の場合、このどちらかに偏ってしまっているという方がほとんどです、というかほぼ90%くらいの確率でどちらかに偏ってると考えていいでしょう。
練習として重要なのは精度と強度のバランスなので、どちらかに偏っているこれら↑の場合、どっちにしてもよろしくないということになるのですが、次にこれらの何がどう良くないのか?という部分について解説していきます。
パターンA:音色は度外視してどんどん音域を広げる
独学の方が陥りがちなパターンです。とりあえず「音色はまぁ何となく意識だけしておいてなるべく高い音まで出そう!その方が練習として効果ありそうだし!」って思ってしまう方が非常に多いです。
しかし音色を全く気にせず音高だけ広がっても、当たり前にその音高を維持するために
- 動いてほしくない部分まで動いてしまう
- 狙って動かしたい部分も過剰に動いてしまう
こんな状態になってしまいます。つまりはどこをどうとっても狙い通りになっていない練習にしかならない可能性が高いです。
質問者さんはアンザッツ4番・6番で音高が上がると音色が5番っぽくなるということで、単純に喉の中で起こっていることを考えれば、咽頭腔が狭まったり喉頭が高くなっているということでしょう。
つまりアンザッツ4と6では本来動かなくていい『口腔を狭くする筋肉/パーツ』や『喉頭を挙上させる筋肉』が動きだすことにもなるし、基本は4番・6番を出そうと意識しているので、5番系統の動きに拮抗する形で主に動いてほしい『口腔を広くする筋肉/パーツ』や『喉頭を降下させる筋肉』も過剰に動いてしまいます。
なのでこのパターンで練習をしても、アンザッツ4・5・6の全てが真っ直ぐ狙った状態になってない、どこをどうとっても美味しくない練習になってしまい、そんな練習状態が長く続いてしまうと喉の筋肉を過緊張させて発声することが常習化し改善するのに非常に時間がかかる固着になってしまいます。
パターンB:音域は度外視し、音色を優先して慎重に練習する
このパターンで練習してしまっている方はそこまで多くないですが
- 毎日しっかり時間をかけて練習しているのにあまり成果がでない
- あまり音高/音量を意識して練習していない
こういう方はあまりに慎重すぎる、というか必要な強度が全く確保できていない練習になっていないか確認する必要があります。
基本的に音域を広げるということは呼気も増えるし、それに耐えるために声帯や喉の緊張も増します。なのでそればかりフォーカスするとパターンAで説明したように各パーツが過緊張気味の発声になりやすいですが、他方で訓練としての強度を調節するのにもっとも影響が大きいのが音域と音量です。
ということは、あまりに音色ばかりをケアして、安全圏でのみの練習しかしていない状態になると、喉にとって必要な負荷がかけられてない訓練しかできていない状態になってしまいます。
ずっとめちゃくちゃ軽い全然負荷にもならないダンベルを使って鍛えようとしている状態なので、時間をかけて練習しても全然効果がでない、変化を感じられないという状況に陥りがちです。
解決方法:どっちも意識する!!!
こんなバカシンプルな解答でいいわけないだろ!と思うかもしれませんが、実際はそんなもんです。これまでにもこの記事のテーマに対する解決方法や対処方法は公開しています。
これら↑の記事を読んでいただければ、ここで書いたような状態になりづらい、ある程度練習に関わる要素を考慮した練習ができると思います。
上で紹介した記事の内容をここでも簡単に解説しておくと
- 練習の要素を決める
- 今回の記事のように音色/音域やそれに関わってくる母音/音量など、自分が意識的に操作できる要素を知っておきましょう
- 練習するときは要素に優先順位を付ける
- 練習の目的に応じて絶対に欠かせない要素とひとまずスルーしてもいいとする要素を考えましょう
- 上記を踏まえたうえでの練習をする
- 何となくふわ~っと練習しても効果は出ません
って感じでしょうか。これらを今回の記事の内容と合わせて考えてみると、音色と音域という要素の優先順位付けがポイントになります。
訓練の段階によっては、極端に要素を絞った練習しかできないということもありますし、訓練が進んだ場合にも狙う要素をあえて絞った、つまり尖った練習をすることもあります。
しかしそれもあくまでトレーナーが意図的に指導/調節し、どれくらいの期間それを続けるのか?という部分が十分に考えられた上でのお話です。
独学の場合は練習の精度自体がどうなってるのか分からないこともあり、要素の優先順位を常に考えながら、できるだけ細かいスパンで変えながら練習する必要があります。
なので音色か音域のどちらかを絶対に欠かせない要素として設定して練習して、それを時間や期間で区切り入れ替えて練習していくのがベターです。
まとめ:優先順位を変えながら練習する
今回の質問者さんの場合
- 狙った発声ができていない場合は開発するのは控えるべきか?
- ある程度は許容して、上の音域も開発しても良いでしょうか?
というどちらの選択がベターか?ということに対して、あれこれ解説してきましたが、回答としてはシンプルで
- ある程度期間を決めて、どちらの方向性でも練習しましょう
ということになります。どちらであっても練習の仕方としては正しいというのがポイントです。
なのでどちらの方向性であっても、片方を全くやらなくなってしまったり、逆に片方しかやらなくなると、恐らく短期間で不調が現れるか、発声状態が全然好転しなくなるはずです。
ここまで色々と書いてきましたが、今現在、自分の練習について悩んでいたり、必要な練習が知りたい場合はぜひ無料体験レッスン(オンライン)にお越しください♪