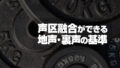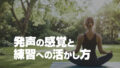ボイストレーニングをある程度の期間続けていくと、成長が鈍化していくタイミングが何度もありますが、その原因はめちゃくちゃ大雑把かつ根本的な原因として
- 練習方法の選択を間違っている
- 練習の強度が低い
上記の2つであることがほとんどですが、これらがボイストレーナーのレッスンを受けていたり、ある程度、自分自身の状態を俯瞰から見ることができてメニュー構成を考えることができるようなレベルになっていたとしても、成長が停滞することがあります。
そういった場合の原因として多いのが、この記事のテーマである『練習メニューと発声状態の固定化』です。
訓練初期の段階では『この練習メニューは◯◯発声のための練習』という風に練習メニューと狙った発声状態をひとまとめに考えることはよくありますが、ある一定のレベルからはそういった固定化が成長するための要素を削ぎ落としてしまっていることがあります。
特定の発声状態と練習方法がリンクしていないか?
- スタンダードな裏声は
- 単音で「オ」母音じゃないとだせない
- スタンダードな地声は
- 上昇型のスケールで「ア」母音じゃないとだせない
上記はボイストレーニングの初期から中期くらいの方によく起こりがちな、練習方法と発声状態が固定化してしまっている例です。またこういったパターン以外にも
- アンザッツの◯番は◯母音だけで練習している
- ミックスボイスの練習は◯◯スケールで◯母音と◯子音の組み合わせだけで練習している
上記のようなこともよくあります。
このような『◯◯を練習するときには◯◯』というような練習方法と狙っている発声状態が固定化してしまうと、ボイストレーニング初級~中級者の方々が陥りがちな『ボイストレーニングの練習自体は上手くなったけど歌うと今までと変わらない』いわゆる “ボイストレーニングが” 上手くなったという本末転倒な状態になります。
練習方法と発声状態がリンクすることのデメリット
ボイストレーニングの最初期、つまり出せる声の中で基準となるものがないような場合、狙った発声状態を必ず起こせる練習方法というのは非常に効果的です。というか最初はそういった練習方法しかできないという状態がほとんどです。
しかしそこから徐々に成長していくと中々変化が起きないというタイミングが訪れます。
その原因は前述の通り、練習方法自体に慣れてしまいそれを繰り返すだけでは訓練として必要な強度が確保できなくなり、脳の神経回路を強化することが少なくなるからです。
「じゃあ1つの練習方法に慣れてきたら、次々に別の練習方法をやればいいんじゃない?」と思うかもしれませんが、それだと同じことの繰り返しになる可能性が大きいです。
つまり新たな練習方法もそれ自体は上手くなるけど発声の自在性は高まることはなく、歌に活かせるような変化も起きないということです。
ではどうすればいいのか?なるべく順調な成長をするにはどういう練習方法がいいのでしょうか?
あらゆる練習方法で『遊ぶ』
- 『◯◯のための練習』を『◯◯』以外の発声で練習してみる
- 純粋な裏声になりやすい練習を支えた裏声でやってみる
- ミックスボイスになりやすい発音・スケールでの練習をミックスせず裏声でやってみる
- 『◯◯になりやすい練習』で『◯◯』とは真逆の状態で練習してみる
- 地声になりやすい要素が多い練習を裏声でやってみる
- 喉頭を下げやすい要素が多い練習を喉頭を上げてやってみる
上記はあくまで一例です、こういった例以外にも練習でもっと遊べるし、そもそも練習というのは自由なものです。何かをガチガチに固めるためにする練習というのはありません。
このブログでも何度か同じようなことを書いていますが、本当に声がにっちもさっちも行かないような状態のときはさておき、ある程度いろいろな声がだせるようになってきたのであれば、練習は適宜変化させてかまいません。


まとめ:システマティックにまとめすぎない
ボイストレーニングに詳しくなればなるほど『◯◯を改善するにはこの母音で~このスケールで~こういう音色で~』とシステマティックに理論を固めてしまいがちですが、どう頑張っても固定された練習メニューだけでは開発できない領域があります。
こういった練習方法のカスタマイズや遊びは、独学で練習している方はもちろん、特定のメソッドを長く学んだボイストレーナーなども同じで、常に意識しておかないと持っている手札だけでなんとか練習やレッスンを進めていこうとしてしまいがちです。
レッスンをしているクライアントさんには口酸っぱく伝えていますが、声であれこれ遊ぶということが成長には絶対に必要です。
決まったルーティーンとしての練習ももちろん重要ですが、それだけを続けていて成長を感じられなくなったのであれば、今回解説したような練習に『遊び』を入れてみてください。
そもそも喉・声を自由にするために練習していたはずなのに、特定の発声・練習だけを上手くこなそうとしていないか?この辺りに目を向けてみると道が拓けるかもしれません。