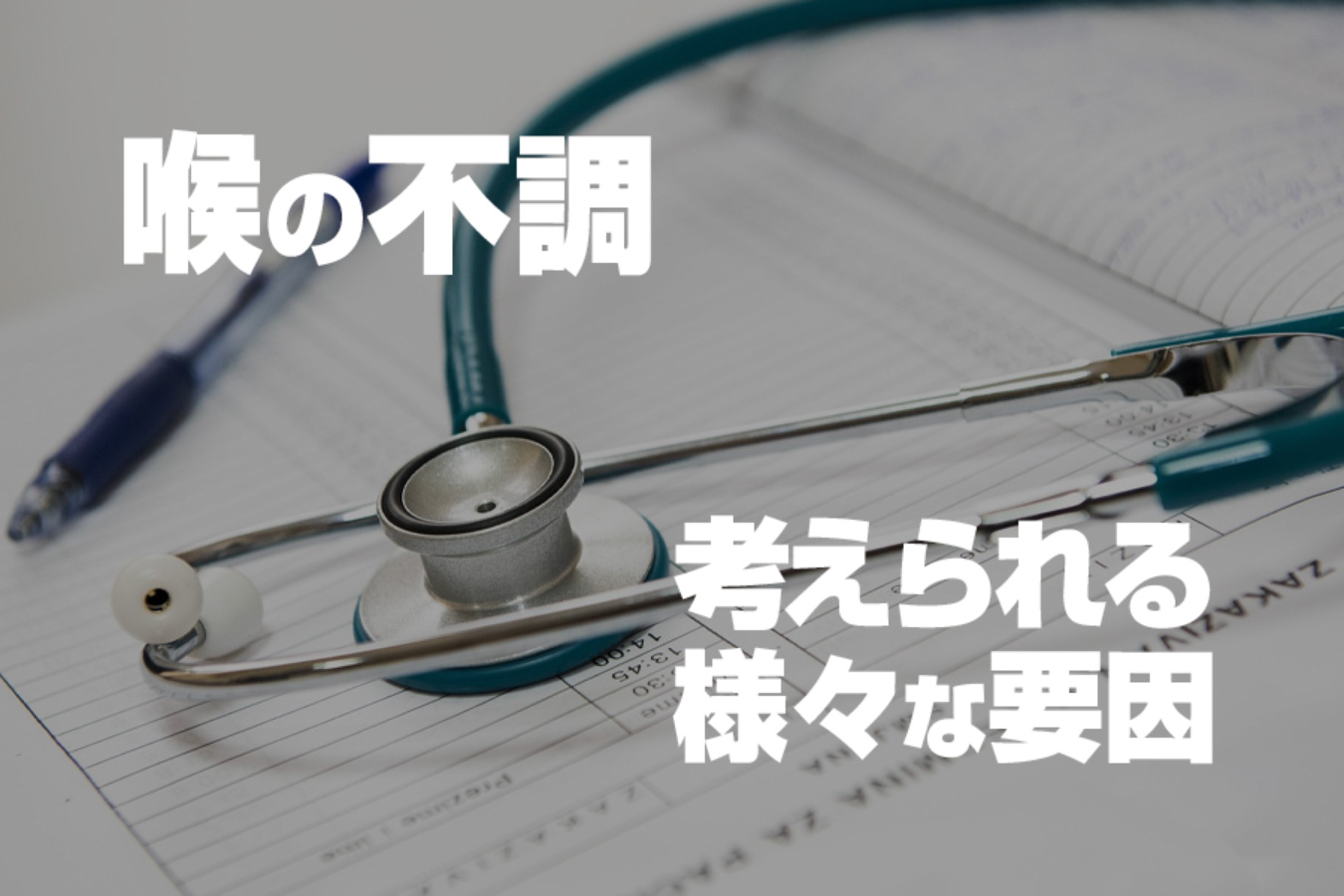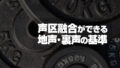毎年、季節の変わり目になると喉に不調がでてしまい、自主練習やレッスンをお休みされるクライアントさんが多くいらっしゃいます。
一週間程度からひと月くらい様子を見れば、徐々に調子が戻るという方が多いですが、重要なのはなぜ声・喉の不調が起きるか?その原因はなにか?ということです。
休めば治る程度の不調であってもそれが繰り返されるとなると、長期的に見れば喉に良くないことは確実です。ということで今回は喉の不調になりえるさまざまな要因について解説していきます。
以前に公開した不調の際に練習するか否かの判断基準については下記の記事をどうぞ。
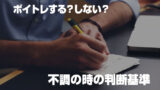
喉の不調の主な症状
- 声が枯れる/掠れる
- 地声/裏声で症状がでる/でないということもありますし、特定の音域だけ枯れや掠れが起こるということも
- 喉に痛みや違和感がある
- 発声すること自体に痛みを生じることもあれば、嚥下時のみ痛みを感じることもあります
- 喉に違和感/疲労感がある
- 明確な枯れや掠れ、痛みはないものの喉が詰まった感じがしたり、疲労感を強く感じることもあります
風邪やインフルエンザ、コロナなどの症状と共に上記のような症状があらわれる場合は、そのほとんどが咽喉の炎症などが原因だとはっきりしていますが、そうではなく上記のような “症状だけ” があらわれる場合には、これらを引き起こしている要因があるはずです。
次に喉の不調の要因として考えられるものを、私自身やクライアントさんの経験からいくつか挙げていきます。
考えられる喉の不調の要因
- 発声に関わる要因
- 練習に関すること
- 精神的なこと
- 環境的な要因
- 飲酒・タバコ
- 乾燥
- 生活習慣
1の発声に関わる要因は自分でも気づきやすく、2の環境的な要因はあまり意識していないこともあり「こんなことが原因で調子悪くなってたの?」と思うことも多いです。
次から一つずつ解説していきます。
喉の不調を引き起こす『発声に関わる要因』
練習に関すること
- 誤った練習メニュー/練習強度の選択
- 癖や固着が強い状態での練習
1の要因は想像しやすいと思います。発声や喉の成長に必要な練習ではなく、偏った練習メニューばかりをやってしまっていたり、練習メニューの選択は正しくとも、その実践の仕方が誤っていると喉になんらかの不調を引き起こすことがあります。
これらの要因で引き起こされる不調は、前述の『喉の不調の主な症状』にある1や3であることが多いです。練習の関する要因で2のような明確な痛みを感じる場合には相当に無茶苦茶な練習をしているということなので、なるべく早くボイストレーナーの指導を仰いだほうがいいでしょう。
他方で意外と盲点なのが2の『癖や固着が強い状態での練習』です。
1のような練習メニューや強度は間違っていないはずなのに、なぜか練習すればするほど喉が不調になるという場合、現状の喉が持っている癖や固着を引きずりながら抵抗する形での練習になるため、喉に違和感・疲労感を感じることがよく起こります。
この場合は適切な休息を取りながら、練習を続けていくことで改善していくことが多いです。
ただボイストレーニングを独学で頑張ってるけれど上手くならない!という方のほぼ90%以上はここで解説した2つの要因を同時に抱えている状態なので、安全かつ滞りなく上達したいのであればボイストレーニングのレッスンを受けましょう。
精神的なこと
落ち込んでいたり萎縮している状態だと当たり前に声が出しにくくなります。精神的な落ち込みによりレッスンや練習に集中できなくなり精度が低下し、結果的に喉に不調が起きてしまうこともあります。
この場合は当たり前に喉に無茶させているわけではないので、不調の症状は喉の違和感・閉塞感などであることがほとんどです。
喉の不調を引き起こす『環境的な要因』
飲酒・タバコ
身体や脳にも良いことのないこれら2つですが、当たり前に喉にもよくありません。
飲酒はアルコールにより喉の粘膜部が乾燥しやすくなりますし、家で一人静かにちびちび飲むならまだしも、ほとんどの飲酒環境は騒がしく人が多い場所だったりするので必然的に声が大きくなってしまい声帯に余計な負担がかかります。
タバコは言わずもがな、煙に含まれる成分は喉や声帯を刺激し炎症の原因になります。
声や喉のことを考えるのであれば、この2つは良いことが全くないので、不調が起こった際にこの記事で解説した要因の中で飲酒・タバコ以外に心当たりがない場合、酒もタバコも一時的にやめてみるか量を減らすなどして様子をみてください。
乾燥
季節の変わり目に不調が起こりがちという場合、空調機器による乾燥が不調の要因であることが多々あります。
特に就寝時に空調機器を稼働させる時期になると、睡眠中の呼吸により喉が乾燥してしまい、起床後しばらく声が上手く出せなかったり枯れ・掠れが起こってしまうことがあります。
この不調に関しては個別で記事にしているので、心当たりのある方はそちらも見てみてください。

生活習慣
生活習慣の中にある不調を引き起こす要因ですが、これは主に2つに分けられます。1つは発声することが直接的な要因で、もう1つは発声とは直接関係のない要因です。
生活習慣の中で『発声することが直接的な不調の要因になるもの』
- 長時間話す/大声で話す
- 運動しながら声を出す
- 睡眠不足の状態で練習/レッスンを受ける
- 頻繁に咳払いをする
これらのほとんどが学校生活や仕事などの社会生活をしていく中でどうしても避けられないという場合が多く、不調を改善することが中々難しいということがほとんどです。
1の長時間話したり大きな声を出す機会が多い場合に不調が起こりやすいということはかなり知られていると思いますが、2の『運動しながら声を出す』というのも不調の原因になりうるということは意外と知られていません。
私のレッスンを受けてくださっているクライアントさんで、宅配便の配達員のお仕事をされている方がこれまで3名いたのですが、3名とも仕事中に重たい荷物を持ちながら電話対応することが多いとのことで、それが原因で過剰なテンションで声帯を閉鎖させるのが癖になっている状態でした。
こういった事例以外にも、筋トレが趣味の方が唸り声をだしながらトレーニングをしすぎて、同じく努力性の発声になってしまっているということもよくあります。
睡眠不足も明確に発声に影響します。粘膜の回復を助ける成長ホルモンは睡眠中に多くその多くが分泌されるため、睡眠不足の状態で発声する機会が多くなると、声帯の回復が間に合わずダメージが蓄積してしまい、徐々に発声しづらくなります。
また意外と不調の要因になりうるけれど意識せずにやってしまっている方が多い咳払いです。声帯には非常に強い刺激なので、あまりに頻繁にやっているとそれだけで不調を引き起こします。
生活習慣の中で『発声とは直接は関係のない要因になるもの』
- 飲食物
- 胃食道逆流症
- 薬剤
練習やレッスンの前に食べたものが唾液の粘稠性を増してしまうもの(糖分の多いものや口内を乾燥させるアルコールなど)だった場合、痰がからみやすくなり結果咳払いを多くしてしまうといった行動に繋がることがあります。
または単純に刺激の強い飲食物(辛いものや酸っぱいもの)を摂取した場合にも、喉に違和感がでたり炎症が起きたりすることもあるので、これまでに解説した要因に心当たりがない場合は、日常的に食べたり飲んだりしているものが不調の要因になっていないか一度精査してみてもいいと思います。
1とも関わってきますが2の胃食道逆流症も意外と気づきにくいですが、明確な喉の不調を引き起こす原因になりえます。
食道粘膜に炎症がある場合は逆流性食道炎と呼ばれますが、そこまでではないけれど胃の内容物が逆流し胸焼けや喉の違和感などを起こしている状態を総称して胃食道逆流症と呼びます。
暴飲暴食や寝る前の食事、前述のようないわゆる刺激の強い食事、アルコール等など、様々な要因で胃液などが逆流し咽喉頭付近にも炎症が起こり咽頭痛や咳、嗄声を引き起こす可能性があります。
まとめ:不調の要因は多岐にわたる
かなり多くの要因を解説してきましたが、当たり前にここには書いていないようなことが不調の原因であることも全然ありえますし、複数の要因が絡み合って不調を引き起こしていることがほとんどだったります。
レッスンをしていても、生活習慣に関わるようなことをご指摘するのはこちらとしても心苦しいのですが、どれだけ正しく効果的であろう訓練していたとしてもそれを栄養として受け取れる喉の状態でなければやはり成長はできません。
酒もタバコもやります!深夜に激辛ラーメンよく食べます!毎日ほとんど3時間くらいしか寝てません!
こういう状況の人はそこまで多くないと思いますが、もしこんな状態だとしたら、どれだけ正しく効果的なボイストレーニングを実践していたとしても、恐らく効果はでません。
そんなトレーニングよりもまずは喉や声帯、というか身体を労った生活をしましょうというめちゃくちゃ当たり前なことに帰結します。
どうやってボイストレーニングをするかも重要ですが、それと同じくらい健康化どうかということも重要です。ボイストレーニングが上手くいっていないと感じる時は今回解説したようなことを一つずつチェックしてみてください。