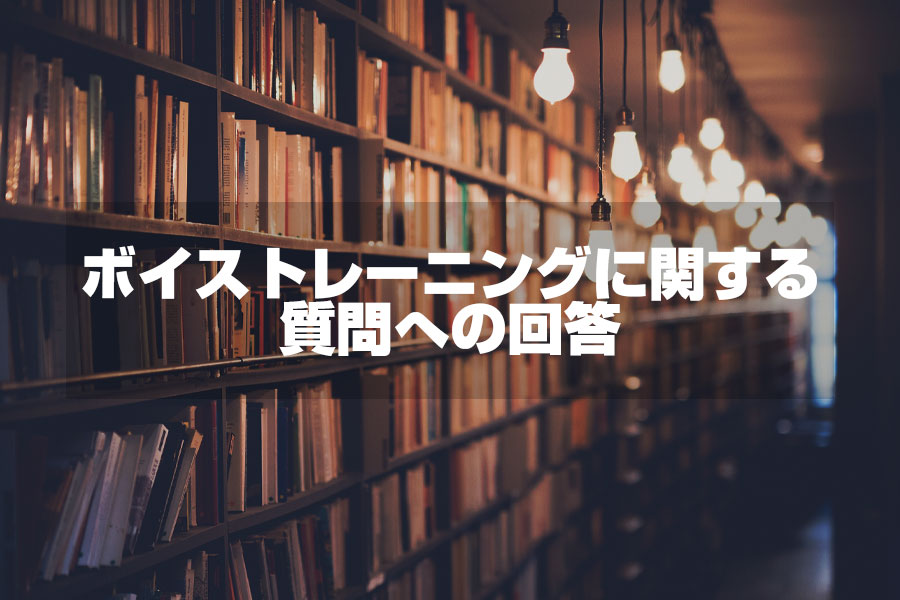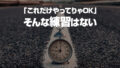2025年中に来た質問・要望への回答です。質問はこちら↓のページからお送りください。
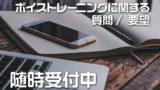
声やボイストレーニングに関する疑問・質問を募集中
数年前まで利用していた質問箱の代わりに、ブログ読者の方が気軽に利用できる質問フォームの解説記事です。…
去年(2024年)の質問回答はこちら↓のページから。
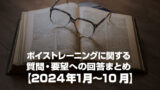
過去の質問/要望への回答まとめページ【2024年】
2024年1月~10月に来た質問・要望への回答です。質問はこちら↓のページからお送りください。回答を…
回答を見たい月をクリックすると
その場所にジャンプします
目次
2025年1月に来た質問への回答
01月10日分
- 質問でなく歌についてのリクエストになりますが、globeのdepartures、原キーでリクエストしてもよろしいでしょうか? 木田先生の歌声でこの曲を是非とも聴きたいです!
- リクエストですね~ありがとうございます m(_ _)m
サビしかしっかりと聞いたことがない曲ですが、かなり難しそうなので少し聴き込んで歌えそうなら歌ってみます!
こちらの記事で詳しく回答・解説しました!
2025年2月に来た質問への回答
02月06日分
- いつも楽しく拝見しております。
倍音唱法に関する記事を読み、私の未熟な耳でもしっかりと倍音が聞こえ感動しました。
木田先生は倍音唱法の他にもデスボイスやホイッスルボイスなどの記事も公開していますが、やはりボイストレーナーにはこういった特殊な発声ができることは必要不可欠なのでしょうか?
私自身が今現在ボイトレレッスンを受けている身なのですが、トレーナーの方はあまり声をお手本を聞かせてくれず、レッスンのほどんどがピアの演奏だけです。
こちらからもっとお手本を聞かせてくれと要求するのも憚られるのですが、先生はどうお考えでしょうか?
- がこのブログで公開しているような、結構特殊な発声まで全て網羅できている必要はないと思いますが、そういった発声ができるような喉の状態や発声のレベルじゃないと、レッスンをしていく上でまともにデモンストレーションできないでしょうね~
こちらの記事で詳しく回答・解説しました!
02月07日分
- とても勉強になるブログ記事ありがとうございます。現在オンラインのボイトレレッスンを受講している20代後半の男です。
現在の声の状態は、習っている先生からミックスボイスはできているから、これから徐々に強くしていく、ベルト化していくというレベルなのですが、その方法が手応えがなく相談させていただきたいです。
ミックスボイスを強くしていくには主に響きを変える、口腔内を広げて硬口蓋に響きを集めて増幅するようにと指導されています。ただこの方法で発声が強くなるイメージが全然できません。
他にも仮声帯?を使うことも指導されていますが、これも上手く現在の声に繋げられるのか疑問です。
木田さんのブログでもミックスボイスを強くする方法は書かれていますが、響きを増幅するということには全く言及されていないため、何か間違っているのか不安です。
長文失礼しました。何かアドバイスいただきたいです。
- 私が考えていることと全く違うのではっきりとは言えませんが、基本的に発声を変化させるということにおいて、もっとも大きな要素は『声帯がどういう状態で振動しているか』なので、ミックスボイスを強くしたいのであれば、所謂共鳴でうんぬんかんぬんということではなく、声帯の接触率・接触のさせ方を変える必要があります。
こちらの記事で詳しく回答・解説しました!
02月17日分
- 私は声と身体の両方をトレーニングしています。
前に、身体の方のトレーニングの負荷をあげたところ、筋肉にハリが残って、身体が硬くなっているのを感じたため、朝の日課にウォームアップ(ハードなラジオ体操みたいなもの)を加え、ウォームアップを行うと声の調子がとても良くなることに気が付きました。
元々、声を出す際にはリップロールや裏声で声を起こす作業を必ず行っていましたが、身体のウォームアップの方が効果が高いのを実感し、ボイトレの前にもウォームアップを行うようになり、それ以来声の調子がとても良いです。
個人的には、ウォームアップを行うことで全身の血流が改善し体温も上がるため喉回りの筋肉も温まり、理にかなっていると感じましたが、木田先生は身体のウォームアップについてどう思われますか?
- とても良いと思います。仰られている通り、身体の大きな筋肉をほぐし血流が良くなると、当たり前に外喉頭筋郡や声帯への血流も改善します。
なのでそういったウォーミングアップをやっていて、日々明らかな効果を感じられているのであれば続けてあげればいいと思います。
ただそういった経験から発声に関わる因果関係がごちゃごちゃにならないように注意する必要もあるでしょう。
貴方の場合、そもそも声のトレーニングが上手くできていたから身体のトレーニングも合わせてやることで相乗効果があったということであり、どれだけ身体のトレーニングをやったとしても、声のトレーニングが上手くできていなかったら、今現在の結果にはなっていないでしょう。
なので今後も声と身体両方のトレーニングを続けるとして、歌や発声を改善したいのであれば、あくまでもメインにすべきなのは声のトレーニングであり、身体のトレーニングがそれに取って代わるようなことになると、途端に上手くいかなくなるはずです。
02月18日分
- 質問ではないのですが、公開されている記事を読んで掲載されている音声を真似していると十日間ほどで明確に声が出しやすくなしました!
無茶苦茶参考になります!今後も利用させて頂きます!
- おお~素晴らしいですね!
今後もどんどん参考にしていただき、上達していってください!( ◉◞౪◟◉)b
2025年3月に来た質問への回答
03月04日分
- フースラー発声学を続けているものの中々行き詰まっている状況の中、声を高くするために甲状軟骨形成術という外科手術について少し検討している状態なのですが、木田さんはこちらの手術についてはどう思われますでしょうか。
フースラーと併用すると普通にトレーニングしていくよりも早く高くて綺麗なミックスボイスがだせるようになるのではと思ってしまいます。
- 質問者さんの状態や目標が分からないので何とも言えませんが、もし何らかの疾患(機能性発声障害等)やジェンダー的な声の悩みを改善したいということではなく、ボイストレーニング的な目的、つまり歌が上手くなりたいという目的のみで手術を考えているのであれば、全くおすすめしません。というか個人的な感覚としては正気の沙汰じゃねぇという感じです。
甲状軟骨形成術などの頸部外切開を伴う手術は何らかの音声障害や喉頭の疾患を治療することが目的です。
比較的安全性が高いとされているこの手術もあくまで治療を目的とし、その効果と身体への負担などを考えればメリットが大きいとされているだけで、身体にメスを入れることには変わりありません。
いくら安全だとしても手術には絶対的にリスクがあります。私は自分の喉に何の病気・障害もないのにも関わらずメスを入れるなんて怖くてとてもとてもできません。それによって今後ボイストレーニングが上手くいくよ!と言われても絶対にしません。
本当に質問文に書かれてあること以外で悩みや目的がないのであればまともな思考ではないので、まずは本気でボイストレーニングに取り組んでみてはいかがでしょうか。
もし「これをやったら今後トレーニングが上手く行くかも?」なんて感覚で手術したとしても、恐らくまた同じように行き詰まって同じような悩みに直面すると思います。
もし質問文には書いていない部分でお悩みがあったり本当の目的は違うところにあるという場合は、失礼なことを書いてしまい大変申し訳ございません。
03月06日分
- アンザッツ4と6を使って裏声を鍛えているのですが、hiC#辺りから少しずつ閉鎖が混ざり、5番的な音色に近づいてしまいます。
そのためメインの練習はhiC#程度までに留めて、時々上の音域に挑戦するようにしています。
高音を開発するためには高いところの裏声が重要だと認識していますが、狙った発声ができていない場合は上の音域を開発するのは控えるべきですか?
ある程度は許容して、上の音域も開発しても良いでしょうか?
- 以前にも記事にしていたはずですが、練習する際に強度と精度のどちらを優先すべきか?というお話ですね。
めちゃくちゃシンプルな回答としては「どっちもバランスよくやってください」ということになります。
アンザッツとしての精度がほぼ完璧に保てる範囲でのみ練習を続ける、逆に精度を犠牲にし狙った状態にはなってないけど音高はどんどん広げていく、これらのどちらか一方の方向性でのみ練習を続けてしまうと、恐らく中々成長・変化が起こらないか、どんどん余計な癖・固着が強くなってしまうでしょう。
こちらの記事で詳しく回答・解説しました!
03月13日分
- 結構前にTwitterで吸気裏声のリスクについての記事を書くとのことで楽しみにしてたんですが、今はもう書く予定はないですか?
- 完全に忘れてました・・・次回の更新分で記事にします!
でも内容はシンプルで『吸気発声だけで訓練を続けると良くないよ~』というだけなので、そんなに真新しいことは書けないですが、しばらくお待ち下さい~
こちらの記事で詳しく回答・解説しました!
03月23日分
- 木田先生、いつもブログの更新ありがとうございます。
大っ変お世話になっております。
早速ですが、木田先生の考えられる「声門上圧」についての見解を伺いたく質問させていただきます。
昨今、ボイトレにおいてさまざまなメソッドや理論が展開されていますが、その中でたびたび見かける声門上圧を重視する考え方に対して、私は懐疑的な見方をしています。
浅学ながら、私は声帯原音の生成に関わる要素は内咽頭筋により調整されるべきであり、外咽頭筋を含む、それ以外の要素は、あくまで補助であるべきで、常に自由に動かせるようにしておかなければ、音色や歌唱表現において不利に働いてしまうのではないか、と、考えております。
仮に口腔内の空間を調整したり、咽頭収縮筋、喉頭蓋の利用によって、理想の声帯振動を得られるとしても、補助輪付き自転車で走るようなものであり、抜本的な解決に繋がるトレーニング、メソッドとは言えないのではないでしょうか……
以上のことから、個人的には、声道を開き、声門上圧を限りなく外気圧に近づける事で上圧を安定させ、声門下圧のみを意識すれば良い状態に持っていく方が、喉はより自然な状態になり、自由度の高い声を手に入れられるのでは、と考えている次第です。
よろしくお願い申し上げます。
- 声門の上・下圧となると内・外喉頭筋以外の要素も多分に含まれ、この質問と回答を読んだ方があまり理解できない内容になってしまいますので、質問文の内容からテーマをシンプルに『ソース/声帯』と『フィルタ/声道』に分けて回答します。
質問者さんは『ソース』つまり『声帯でできる原音』こそ重視すべきであり、昨今の『フィルタ』つまり子音/発音やスケールの作用による声道/共鳴腔の操作を絡ませ、そこを重要視する発声訓練はどうなのか?と思ってらっしゃるということになります。
>抜本的な解決に繋がるトレーニング、メソッドとは言えないのではないでしょうか
はい、私も基本的には質問者さんと同じ考え方なので、この意見には同意します。
ただ重要なのは抜本的な解決に至るまでの道が抜本的な練習方法だけでは全く見つからないといった喉の状態の方は非常に多いということです。
つまり声道の形状やその他声門上のパーツによるサポートがない状態だと、まともに声帯のコントロールができない、なのでまともな訓練にならないというレベルの方も多いです。
訓練の段階の最初から最後まで声道操作の多大なサポートありきで発声を作り上げていくのは全く賛同できませんが、要所要所でその時々のレベルにあったソース・フィルターの連動を促す訓練は有用だと考えています。
>声道を開き、声門上圧を限りなく外気圧に近づける事で~
この辺りの記述は同意する部分と同意できない部分がありますね。発声訓練の初期・中期にはそういった考え方で訓練を進めた方がスムーズに上手くいく場合もあるし、その方向性でも問題ないことも多いかと思います。
ただ最終的にどういった声を出したいかということに左右されますが、どうやってもフィルターの形状によるブーストが必要な声もあります。
それらが仰られている『声道を開き、声門上圧を限りなく外気圧に近づける』という声の作り方では達成できないので、最終的にはソースとフィルタのバランス取りは必要だということになります。
ただ最終的には両方の要素が必要だしそのバランスが重要なのですが、あくまでも訓練として重要で常に意識しておかなければいけないのは声区と母音だと考えています。恐らくこの辺りも質問者さんと同じような意見なんじゃないかな~と思います。
03月25日分
- 吸気裏声の記事を読んで吸気裏声を練習してみましたが、呼気と裏声を比べて硬い閉鎖が混ざったような裏声になってしまいます
初めはこんなもんでしょうか?
もっと柔らかく出せる高さから練習した方がいいですか?
- ブログでも何度かヒントっぽいものは書いていたと思うのですが、レッスンでも聞かれることが多いので次回の更新記事で取り上げようと思います。しばらくお待ち下さい。
こちらの記事で詳しく回答・解説しました!
2025年4月に来た質問への回答
04月10日分
- 髭男のPretenderを解説込みて聞きたいです!
- なんだかめちゃくちゃ難しい曲ばっかりリクエストされますね笑
レッスンでも結構取り扱ったことがあるので、今度歌ってみます~
こちらの記事で詳しく回答・解説しました!
04月11日分
- いの母音が苦手です。
ヘッドボイスでhiA~hiDくらいだったら綺麗に出せていると思っているのですが、ミックスボイスだとかなり裏返りが起きます。
いの母音で強いミックスボイスを出すのは難しいのでしょうか?
できれば解説してほしいです。
- 「イ」母音は高音域を出しやすくはあるんですが、強い音で鳴らそうとすると難易度が上がる少しトリッキーな母音なんですよね~
こちらの記事で詳しく回答・解説しました!
2025年8月に来た質問への回答
08月24日分
- はじめまして。
息の使い方(?)に関して悩んでいるので質問を送らせていただきます。
自分は30代の女性で、ボイトレのレッスンを受け始めて2年ほどになります。
複数の講師の方に見ていただいている(※そういうシステムのレッスンに通っています)状態なのですが、「息の量が足りていない、声帯の閉鎖が強すぎる」「息が多すぎる、声帯の閉鎖が足りなさすぎる(普段の話し声からしてややハスキーっぽいので声帯を開く癖がついているのでは)」と真逆の指導を受けることが度々あります。
自分では息が多い自覚はなく、喋っている時に「苦しそうに聞こえる」「(歌と関係なく)息が圧倒的に足りてないのでは」と言われることが多いので息の量が足りていない(声帯が締まりすぎている)方が正なのでは、という自認なのですが、息が多すぎるように聞こえてしまう原因などは何かあるのでしょうか。
(声帯周りはカメラで確認して問題ないことを認識しております)
また息が多すぎるように聞こえてしまうことを改善できるのであればその方法も教えていただきたいです。
普段はあまり大きな声を出せる環境にないので、息を長く吐きながら止めたり流したり、ハッハッと短く切るようにしたり、エッジボイスを色んな音程で出すようにしたり等の練習しか出来ていません。
また我ながら不思議なのですが、自宅での練習ではある程度自由にエッジボイスが出せるのにレッスンの時間になると絞り出すようなエッジボイスしか出せなくなってしまいます。
- 『声帯の閉鎖が強すぎる』と『息が多くて閉鎖が弱い』は別に真逆の状態ではなく、どちらの要素・原因が割合して大きいかというだけの話なので、トレーナーがどちらの症状を先に解消しようとしているかによって指導方法が変わってきます。
こちらの記事で詳しく回答・解説しました!
2025年10月に来た質問への回答
10月15日分
- 高い声を出そうとすると、喉がつまるのですが、これはどういうメカニズムなんでしょうか?
- よく聞かれる悩みですが、意外と真正面から解説したことなかったので、次回更新する記事で回答します。
こちらの記事で詳しく回答・解説しました!